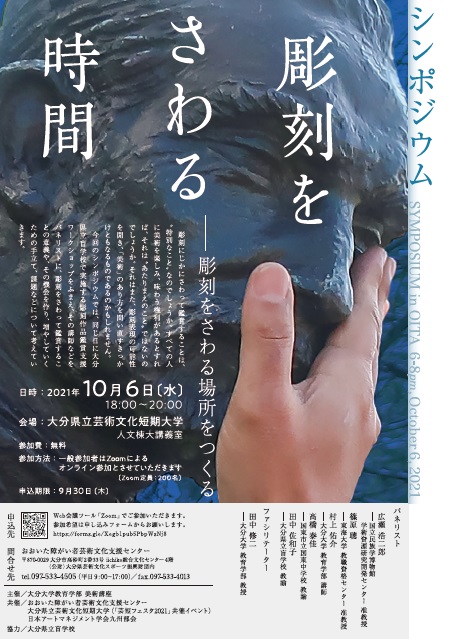日本アートマネジメント学会では、2023年6月11日に研究会「共生社会とアートマネジメント」 を開催します。
兵庫県立尼崎青少年創造劇場(ピッコロシアター)が取り組む「共生社会づくり」は多彩なラインナップがありますが、今回は2つに絞り、お話ししていただきます。1つには、兵庫県小野市で続けている、在留外国人と日本人をつなぐ演劇ワークショップ「にほんごであそぼう」です。もう1つは、聴覚や視覚に障害のある方に対する演劇作品の「鑑賞サポート」の試みです。
障害者文化芸術活動推進法が2018年に、障害者情報アクセス法が2022年に施行されました。これからの文化施設や文化団体の現場では、文化芸術をユニバーサルに届けることができるのか、どうしたら表現する権利を守れるのか、の課題に直面しており、本研究会を発案・開催いたします。
兵庫県立ピッコロ劇団より俳優のお2人をお招きし実際の技法を実演してもらうほか、参加者にも簡単なワークショップを体験していただきます。また、終了後は交流会を開催いたします。会員・非会員問わず、どなたでも参加可能ですのでぜひご参加ください。
日 時|2023年6月11日(日)午後2時~午後4時(受付開始 午後1時45分~)
※終了後に交流会を開催します。
ゲスト|本田千恵子さん、菅原ゆうきさん(兵庫県立ピッコロ劇団 劇団員)


場 所|アカデミックスペース「本のある工場」(大阪市此花区西九条5丁目3番10号)
※最寄り駅:JR大阪環状線・阪神なんば線 西九条駅下車 。徒歩7-8分
※階段で2階の会場に上がります。エレベーターはございません。
対 象:文化施設・文化団体、文化の現場で活動するスタッフ、アートマネジャーなど
定 員:30名(要事前申込、先着順)
※会員・非会員問わず、どなたでも申込可能です。
参加費:1人1,000円(ドリンク・お菓子付、持ち込み歓迎)
【お申し込み】
専用フォームよりお申し込みください。お申し込みフォームはこちら
定員に達したため、お申し込みを締め切りました(5/31)
※お申し込み後、キャンセルされる際は、必ずご連絡をお願いいたします。
【お問い合わせ先】
お問い合わせ:jaam1998.office [a] gmail.com (日本アートマネジメント学会)
※ [a] を@に変更して送信してください。